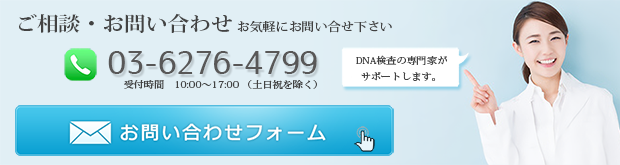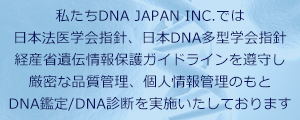ゲノミクス
「○○ミクス」・・この語原は、1980年代に登場したゲノミクス(オーミクス)を一捻りしたものかも知れません。

その生物の遺伝情報を全て解読してみましょうと言うのが1980年代に始まりました。最初に完全解読されたのはファージと呼ばれるウイルスです。
これ以降、さまざまな生物のゲノムを解読する事となり、ヒトゲノムの配列はヒトゲノムプロジェクトによって、2003年ヒトゲノム精密配列決定されました。
すでに解読済みの全ゲノム塩基配列をもとに、その生物の全ての遺伝子の発現量を網羅的かつ統計的に解析することを「ゲノミクス」と呼びます。
つまり解読されたゲノム情報をグループ化し詳細に調べましょうと言うことです。
まず、全ゲノムをテーブルに乗せて全貌をみると、ただ、ひたすら塩基がズラーと並んでいるだけです。
そこで塩基配列をながめ、様々な特徴を見つけ出します。
たとえば、ここに塩基配列が繰り返している所があるとか、塩基配列が繋がっている所があるとか、そしてそこに一づつ名前を付けていきます。
この技術をアノテーションと呼びます。
そこから別の学問に進化し、ゲノム情報科学(ゲノムインフォマティクス)と呼ばれる分野が誕生しました。
これをきっかけに、比較ゲノミクス、機能ゲノミクス、薬理ゲノミクス、毒物ゲノミクス、メタジェノミクス、プロテオーム等々、さまざまな分野の学問が誕生したのです。
~オームと~ミクス
生化学の世界で「~オーム」とか「~ミクス」と呼ばれる言葉が氾濫しています。
では、この類の言葉の語原は何かと調べてみるとトランスクリプトーム(transcriptome)これは、一つの生物において転写されている全ての転写産物を意味する言葉で、Transcript=転写 + genome=ゲノムの融合語です。
このトランスクリプトームは、非常にゴロが良く、おおいに受け入られました。そしてこれを真似て次々と融合後が生まれました。
タンパク質やRNA、ペプチドなどの包括的な呼び方として、プロテオームやペプチドームなどが作られ、物質だけでなく代謝経路や代謝ネットワークであるメタボロームなども作られました。
そして、トランスクリプトミクス(transcriptomics)が生み出されました。
このトランスクリプトミクスは、ゲノム情報を利用して、一つの生物や細胞に含まれる全ての転写産物について網羅的・系統的に発現動態などを解析する意味を持ち、トランスクリプトームを扱う学問とされています。
これらは、オーミクス (omics) と呼ばれ「研究対象+omics」という名称を持つ生物学の研究分野とされ、ゲノミクスとは、「遺伝子(gene)+omics」=genomicsゲノミクスと呼ばれるようになりました。
私たちDNA JAPANでは、このゲノミクスの技術を用いた研究と開発も行っています。